 ハイケ・ブルック、スマントラ・ゴシャール(野田智義訳)「意志力革命~目的達成への行動プログラム」、ランダムハウス講談社(2005)
ハイケ・ブルック、スマントラ・ゴシャール(野田智義訳)「意志力革命~目的達成への行動プログラム」、ランダムハウス講談社(2005)
お奨め度:★★★★★
この種の本としては、非常に体系的、かつ、論理的である。まず、これが第一印象。そして、読み出すと、引き込まれる。現実を踏まえた問題提起とその問題に対する具体的な解決法が述べられている。
「あくせくしながらも結果として何もしていない」状態から、自らの意志を駆使し、目的意識を伴う行動をとって有意義な結果をもたらすことが出来るようにしていく。そんなことができればいいなと思う人には必読書。
組織(経営)が目的達成するために個人が行動をするという視点から、マネージャー、リーダー、個人がどのような取り組みをすればよいかをそれぞれの視点からプログラムとして具体的に書かれている。
この構図は、プロジェクト、母体組織、メンバーで、プロジェクトの目的を達成するにはどうすればよいかという問題にそのまま適用できそうである。
成功企業十数社の具体的な事例をもとに書かれている。このような事例が提示されていること自体、ちょっとした驚きであるし、この本の魅力でもある。
個人が成長し、組織が変わらないと、個人がジレンマに陥る。その点を無視した組織の中で活動する個人の成長論というのは現実性に乏しい。この本のすばらしさは、そこの連鎖を十分に意識している点にある。
難点は、かなり、抽象度の高い記述になっている。かなり、本気で読まないと難しい。そのような本気が報われる本でもある。
あとがきもよい。この本の著者のひとりであるスマントラ・ゴシャールは、訳者の野田氏によると、稀有の経営学者だそうで、この本を世に出してすぐに他界したそうだ。野田氏は「異才」という表現を使っているが、まさにその言葉を彷彿させる本である。
そのスマントラ・ゴシャール博士の活動について、エピソードを交えて詳しい解説がされている。この解説を読むと、本書の読解の助けになるだろう。
 モーガン、マッコール(金井 壽宏、リクルートワークス研究所訳)「ハイ・フライヤー―次世代リーダーの育成法」、プレジデント社(2002)
モーガン、マッコール(金井 壽宏、リクルートワークス研究所訳)「ハイ・フライヤー―次世代リーダーの育成法」、プレジデント社(2002)






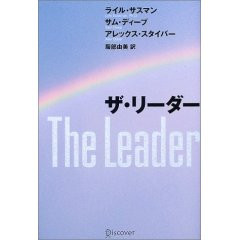

最近のコメント