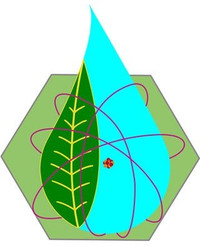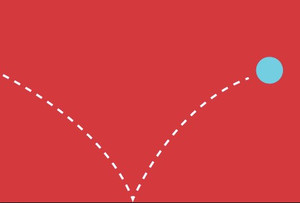【マネジメントスタイル:雑談5】VUCAの時代の「新・現場主義」~自律分散型組織をつくる
◆はじめに
現場主義は戦後の日本の高度成長の源泉だったということに異議がある人は少ないでしょう。一方で、今、日本の成長が止まっている原因になっているのが現場主義だと考えている人も少なくないと思います。
今回は、なぜこうなったのか、そしてVUCAというパラダイムシフトの中で、これからどうすべきなのかを考えてみたいと思います。
結論だけ書いておきますと、VUCAの時代に必要なのは今では私語になりつつある、現場主義です。ただし、従来の現場主義ではなく、新しい現場主義だというのがこの記事で言いたいことです。
◆日本の現場主義
戦後の大量生産の時代の競争力の源泉は事業による利益でした。そして、それを実現していたのは、経営(者)でした。
単純にいえば、企業は新しい製品を考え、生産のための設備投資し、製品を生産し、販売して利益を出し、それを活用して設備を拡充し、生産量を増やすことによってコストを下げ、製品価格を下げることによって売り上げを増やし、利益を増やすというモデルでした。このサイクルを繰り返し、企業は競争力を高め、成長していきます。
またこの延長線上で、利益を全く新規の製品の開発に活用し、新しいコンセプトの製品を作りました。これにより、製品ラインナップを充実させるとともにブランドができ、競争力を高めてきました。
この世界的な流れに楔を打ったのが、日本の現場でした。
日本の現場は製品の新規性ではなく、コストを下げることと品質を向上させることの両立で競争力を持つことを考えました。簡単にいえば、製品コンセプトとのもはいわゆる先進国で開発されたものを真似て、生産方法に工夫を加えることによって、より安いコストでより高い品質の製品をで作るというチャレンジに成功し、高度成長を成し遂げました。
ここで注目すべきは、加工方法やプロセスの工夫をしたのは経営スタッフではなく、現場で働く人だったことです。現場を徹底的に教育し、育て、コストを下げ、品質を高めるための工夫をする意識づけをしました。いわゆる改善活動と呼ばれるものです。
最大の日本企業であるトヨタが改善の繰り返しによって成長してきたことは注目に値します。一方で、もともと改善は新しいコンセプトの製品を生み出そうという活動ではなかったことに注意をしておく必要があります。
従来の現場はこのような活動をしていたわけですが、その背景には欧米ではできなかった現場への権限移譲があります。生産方法を現場で工夫するために、現場がある程度自律的に活動できるように現場の監督者に大きな権限を委譲し、現場を動かしていました。これが日本企業の現場主義です。
余談になりますが、日本は海外進出するときにこのような権限移譲を現地に導入しようとしますが、欧米ではほとんど失敗しています。欧米では経営と現場の立場の違いを明確にしているため、思った以上に現場への権限移譲という壁が大きかったためです。