文章を書いて考える
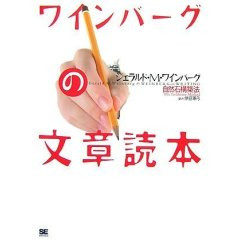 ジェラルド・M・ワインバーグ(伊豆原弓訳)「ワインバーグの文章読本」、翔泳社(2007)
ジェラルド・M・ワインバーグ(伊豆原弓訳)「ワインバーグの文章読本」、翔泳社(2007)
お薦め度:★★★★1/2
(原題:Weinberg on Writing: The Fieldstone Method)
メルマガを発行し始めて6年になる。かなりの頻度で書いているし、最近はブログも書いている。最初のうちは、移動のときとかに予め何を書こうかというあらすじを考えておき、机に座って一気にかくという方法を取っていた。ところが2~3年前から明らかにスタイルが変わってきた。予め考えておくのはテーマくらいで、書きながら考えるようになってきた。そして、最近、感じるのが、書くことによって考えることができるようになった。
普段、あまり文章を書きなれていない人はこの微妙な感覚の違いはぴんとこないかもしれないが、書くことによって考えるというのは、文章をあれこれいじることで頭の整理ができたり、発想ができたりすることができるようになってきた。
さて、前置きが長くなったが、ワインバーグに憧れる人は多いと思う。ソフトウエアサイエンスでは、マネジメントのトム・ピーターズのような存在である。ワインバーグの何がすごいかと改めて考えてみると、やはり、文章である。非常に深い思考を短い文章の中に凝縮する文章術は本当にすごいと思う。若いころからずっとあんな文章が書けないかと思っている。
そのワインバーグの文章術をまとめた本がでた。これだ。とりあえず、レッスンがあるので、やってみた。書いていることをきちんと理解できていると、びっくりするくらい、ワーンバーグみたいな文章が書ける。
ぜひ、読んで、試してみてほしい。
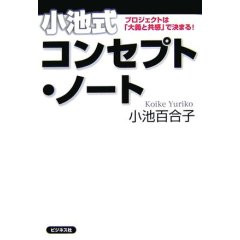
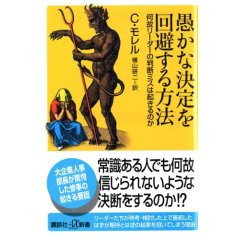
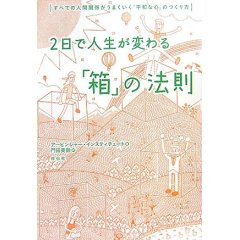
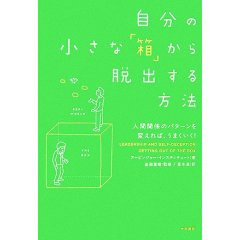
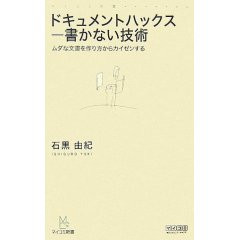
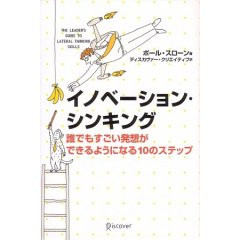
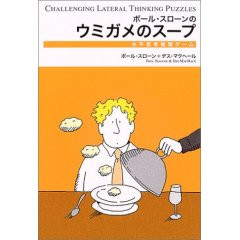
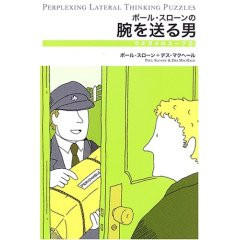
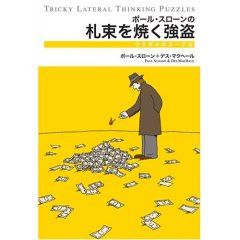
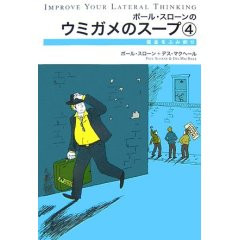
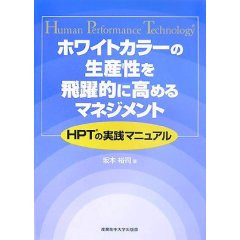
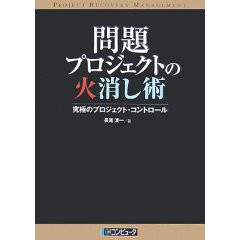

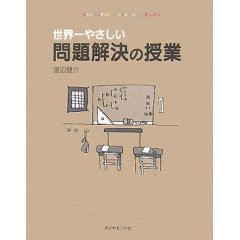
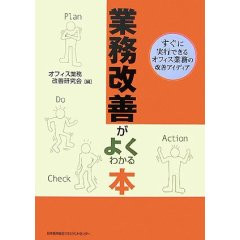

最近のコメント