現代の管理職に求められるものと、その達成方法を学ぶ
 樋口 弘和「理想の上司は、なぜ苦しいのか: 管理職の壁を越えるための教科書 (ちくま新書)」、筑摩書房(2012)
樋口 弘和「理想の上司は、なぜ苦しいのか: 管理職の壁を越えるための教科書 (ちくま新書)」、筑摩書房(2012)お奨め度:★★★★★
管理職のあり方について書いた本は多いが、この本は、管理職に求められるものがどのように変わってきたか、そして、その変化にどのように対応していけばよいかを解説している。
 樋口 弘和「理想の上司は、なぜ苦しいのか: 管理職の壁を越えるための教科書 (ちくま新書)」、筑摩書房(2012)
樋口 弘和「理想の上司は、なぜ苦しいのか: 管理職の壁を越えるための教科書 (ちくま新書)」、筑摩書房(2012)
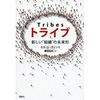 セス・ゴーディン(勝間 和代訳)「トライブ 新しい“組織”の未来形」、講談社(2012)
セス・ゴーディン(勝間 和代訳)「トライブ 新しい“組織”の未来形」、講談社(2012)
お奨め度:★★★★★
稀代のマーケッタであり、コンサルタントであるセス・ゴーディンの新作。翻訳は勝間和代さんで、彼女自身が持ち込んだ企画だそうだ。まえがきに、自分自身はこの本が出る前からこういう活動をやっていたよと言わんばかりの自身の活動を書かれているのが本としてはちょっと残念だが、トライブという概念自身は本物で、本もよい本だと思う。自分の活動スタイルを模索している人には、ぜひ、一読をお奨めしたい。
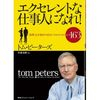 トム・ピーターズ(杉浦 茂樹訳)「エクセレントな仕事人になれ! 「抜群力」を発揮する自分づくりのためのヒント163」、阪急コミュニケーションズ(2011)
トム・ピーターズ(杉浦 茂樹訳)「エクセレントな仕事人になれ! 「抜群力」を発揮する自分づくりのためのヒント163」、阪急コミュニケーションズ(2011)
お奨め度:★★★★★+α
※facebook記事「ディス・イズ・トム・ピーターズ」
トム・ピーターズ総集編な一冊。この本の原題は、「The Little BIG Things」。タイトルから分かるように、小さく大きなこと。
この本は内容を紹介しようとは思わない。トム・ピーターズの望むようにトイレで読んで欲しい。この記事は、読者の方にこの本を手に取っていただくことを目標に書く。
橋本 忠夫「変革型ミドルのための経営実学―「インテグレーションマネジメント」のすすめ」、芙蓉書房出版(2010)
お奨め度:★★★★★
サントリーで情報システム部長、事業部企画部長、工場長、商品開発研究所長、SCM本部長、取締役、サントリー食品工場社長などを歴任され、現在は多摩大学大学院で教鞭をとられている橋本忠夫先生が、複雑化する経営環境に対応していくために、ミドルマネジャーの連携による新しいマネジメントの形として「インテグレーションマネジメント」を提案された1冊。インテグレーションマネジメントというアイデアもさることながら、おおよそ、現代の大企業で起こっているさまざまな問題に対して、体系的に納得性の高い分析が行われており、ミドルがマネジメントの視座を考えるには最高の一冊。
フランク・アーノルト(畔上 司訳)「有名人の成功のカギはドラッカーの「マネジメント」にあった」、阪急コミュニケーションズ(2011)
お奨め度:★★★★★+α
成功者(有名人)48名のマネジメントのベストプラクティスを、「組織のマネジメント」、「イノベーションのマネジメント」、「人間のマネジメント」の3つの分野に分け、著者の視点から紹介した一冊。1人1テーマにまとめられているが、テーマ意外にも学ぶところが多い。48名のリストとベストプラクティスは記事の最後にリスティングしている。
=-=-=-=-=
「ファンが選ぶビジネス書」はfacebook別館で、5人以上のリクエスト(いいね!)があった書籍の紹介です。詳しくは、こちらをご覧ください。
=-=-=-=-=
ピーター・ドラッカー、ピーター・センゲ「DVDだからわかる ドラッカーのマネジメント理論~実践型マネジメントワークブック」、宝島社(2011)
お奨め度:★★★★★
第1部は、ドラッカー財団の代表であるフランシス・ヘッセルバインが司会を務め、マネジメントの父ピーター・ドラッカーと組織学習協会会長ピーター・センゲによる「変化の時代をリードする」という対談。1999年に、ドラッカーの家で行われたもの。第2部は、第1部を踏まえて行うワークブックになっている。
 阿久津 一志 「「職人」を教え・鍛え・育てるしつけはこうしなさい!」、同文館出版(2011)
阿久津 一志 「「職人」を教え・鍛え・育てるしつけはこうしなさい!」、同文館出版(2011)
お奨め度:★★★★1/2
左官のサービス業を営む著者が、同業の経営者をターゲットに、「職人」育成について、体系的に解説した一冊。体系的でありながら、自社での具体的な取り組みを豊富に紹介されている。自社の左官職人を念頭において書かれた本であるが、ロジカルな取り組みが多く、どのような分野の職人にも通用する。特に、著者の会社は少数誠意を目指しているため、ソフトウエアの現場を育成するマネジャーに非常に参考になる。
 ヘンリー・ミンツバーグ(池村千秋訳)「マネジャーの実像 「管理職」はなぜ仕事に追われているのか」、日経BP社(2011)
ヘンリー・ミンツバーグ(池村千秋訳)「マネジャーの実像 「管理職」はなぜ仕事に追われているのか」、日経BP社(2011)
お奨め度:★★★★★+α
1973年に「マネジャーの仕事」でマネジャーのイメージと実態のギャップを明らかにし、以来、「人間感覚のマネジメント―行き過ぎた合理主義への抗議」で人間の次元でのマネジメントの重要性を説く。また、「戦略サファリ」で従来から考えられてきたサイエンスとアートの統合だと考えられてきた戦略計画の策定に「クラフト」という新しい視座を提唱。最近では、コミュニティーとリーダーシップを合わせたコミュニティシップを提唱するなど、常に、マネジメントに新しい視座・視点を提案してきたミンツバーグ博士の36年間の足跡とともにドラッカー以来のマネジメントに関する多くの経営学者や心理学者の知見が一望できる一冊。そこから見えてくるものは、懐古ではなく、創造であり、実践である。
 安宅和人「イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」 」、英治出版(2010)
安宅和人「イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」 」、英治出版(2010)
お奨め度:★★★★☆
マッキンゼー・アンド・カンパニー出身の著者が書いた課題設定型の問題解決の本。イシューという概念を持ち込み、イシューをどのように作り、どのように分析し、どのようにプレゼンするかを魅力的にまとめた本。ビジネスパーソンが生産性を向上させるためには不可欠な考え方である。また、プロフェッショナルな仕事をするためにも不可欠である。プロフェッショナルを目指すすべてのビジネスパーソンに読んでほしい。
最近のコメント