 クリス アンダーソン(篠森ゆりこ訳)「ロングテール―「売れない商品」を宝の山に変える新戦略」、早川書房(2006)
クリス アンダーソン(篠森ゆりこ訳)「ロングテール―「売れない商品」を宝の山に変える新戦略」、早川書房(2006)
お奨め度:★★★★1/2
80:20の法則というのがある。
最近、格差でよく話題になるが、イタリアの経済学者・社会学者、ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto)が、欧州各国や米国の統計データに基づいて統計的に所得配分の研究を行い、一部の人たちに大部分の所得が配分されていることを発見した。
この発見が後に、いろいろな人たちの手によって、さまざまな自然現象に当てはまることが指摘し、「不良全体の80%は、20%の原因に由来する」「売上の80%は、全商品の20%が作る」「売上の80%は、全顧客の20%によるものである」といったルールが生み出されていった。これらは、80:20の法則と呼ばれる。
ついでに、米国の品質管理のコンサルタントジョセフ・M・ジュラン(Dr. Joseph Moses Juran )は、こうした普遍的現象を品質管理に適用することを提唱し、品質管理の分野では「パレート原則」として有名である。
さて、こののテーマ、ロングテールは、ネットワーク経済の市場においては、80:20が必ずしも成り立たないことを指摘した話題の本である。著者のアンダーソンはWIREDの編集長で、もともと、WIREDに書いた記事が話題を呼び、書籍として出版されたという経緯がある。
この本は次のような事例の紹介で始まる。ジュークボックスに入っている曲1万曲の中で、3ヶ月に最低一回はかけられる曲が何%あるかという話。80:20の法則だと、20%ということになるのだが、なんと、この答えは98%だそうだ。
ここからiPodのダウンロードサービスが同じような傾向を持つことは容易に想像できる。この本では、このような現象を統計学のロングテール分布になぞらえてロングテールと呼び、今、さまざまな分野で、このような現象が起こっていることを実証している。
実際に、自分自身の消費行動を見てもこの傾向は強くなっている。日用雑貨のようなものでも、手に入るもので済ませようという考え方から、楽天を検索すればどこかで手に入る(多少、送料はかかるが)という感覚が強くなってきている。
この本は、このようなロングテール商品を起点にして、今後、ビジネスが如何に変容していくかを論じている。Web2.0などの背景にはこのような思想があり、これからのビジネス環境を理解する上では、必読の1冊だといえる。
最後の章で、ロングテールのビジネスの成功法則が書かれている。
法則1:在庫は外注かデジタル
法則2:顧客に仕事をしてもらう
法則3:流通経路を広げる
法則4:消費形態を増やす
法則5:価格を変動させる
法則6:情報を公開する
法則7:どんな商品も切り捨てない
法則8:市場を観察する
法則9:無料提供を行う
如何だろうか?成功しているネットビジネスプレイヤーでは、もはや、あまり前になっていることが並んでいる。
 石川昭、辻本 篤編「新製品・新事業開発の創造的マーケティング―開発情報探索のマネジメント」、生産性出版(2006)
石川昭、辻本 篤編「新製品・新事業開発の創造的マーケティング―開発情報探索のマネジメント」、生産性出版(2006)
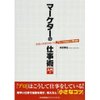
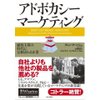
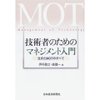
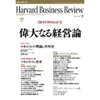



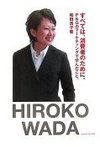

最近のコメント