女子高生の目からみた会社経営
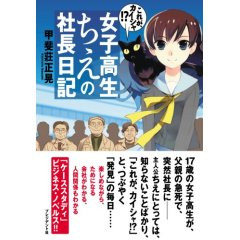 甲斐莊正晃「女子高生ちえの社長日記―これが、カイシャ!? 」、プレジデント社(2007)
甲斐莊正晃「女子高生ちえの社長日記―これが、カイシャ!? 」、プレジデント社(2007)
お奨め度:★★★★1/2
TBSの日曜日のドラマで「パパとムスメの7日間」というのをやっている。父とムスメが電車事故で幽体離脱して入れ替わって、それぞれの立場で会社に行ったり、学校にいったりするというコメディドラマ。究極の世代間コミュニケーションだ。この中で、ムスメがパパとして仕事をして、常識にとらわれない発想をし、活躍する様子はなかなか興味深い。
知らないことの強さのようなものもあるが、どうも、余計なことを考えすぎている部分も少なくない。シンプルに考えると別の世界が見えてくるわけだ。問題に遭遇したときに、もし、自分が常識も組織に関する情報もまったく持っていなかったとすればどう判断するか?
これが求められるような時代になったきたように思う。
このビジネスノベルは17歳の女子高生が、父親の急死で、突然社長に―。主人公ちえにとっては、知らないことばかり、「これが、カイシャ!?」と、つぶやく「発見」の毎日といったストーリー。
この本は単に経営の入門書というだけではなく、商品開発、営業、工場での生産などを、女子高生という素人の目から見て、どう見えるかを示しているのがミソ。たいへん、わかりやすいので、入門書としてもよいが、ある程度、経験がある人も新たな発見があるのではないかと思う。
なかでも、日本組織の特徴である人間関係に関する部分が面白い。日本人は何にこだわっているのかという思いになるのではないかと思う。
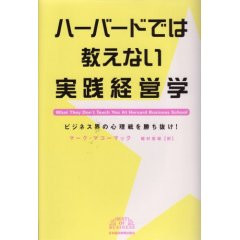
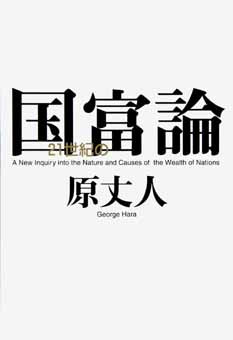
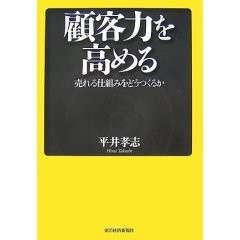
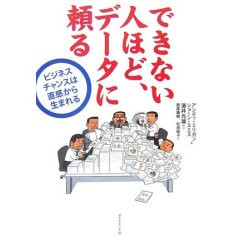
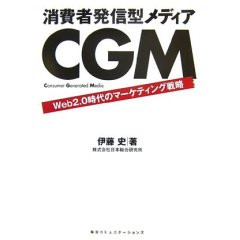

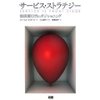

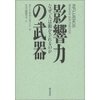

最近のコメント