システム思考で「匠に呪縛」から解放されよう!
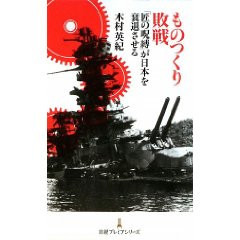 木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
お奨め度:★★★★★
日本の技術が苦手なのか、「理論」、「システム」、「ソフトウエア」を3つだという仮説に基づく、システム思考を中核に据えた技術マネジメント論。
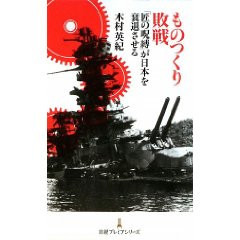 木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
お奨め度:★★★★★
日本の技術が苦手なのか、「理論」、「システム」、「ソフトウエア」を3つだという仮説に基づく、システム思考を中核に据えた技術マネジメント論。
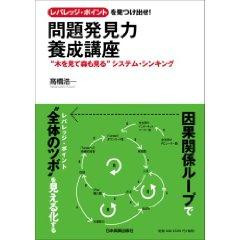 高橋 浩一「レバレッジ・ポイントを見つけ出せ! 問題発見力養成講座 “木を見て森も見る”システム・シンキング」、日本実業出版社(2009)
高橋 浩一「レバレッジ・ポイントを見つけ出せ! 問題発見力養成講座 “木を見て森も見る”システム・シンキング」、日本実業出版社(2009)
お奨め度:★★★★★
日本でのシステム思考のエバンジェリストの一人、高橋浩一さんのシステム思考の書籍が出た。
システム思考をやっている人と話をしていると、他のフレームワークと組み合わせることを嫌う人が多い。そのために、どうしても、教科書的な感じの本が多いのだが、そんな中で、この本は、システム思考と他のフレームワークを組み合わせる提案をしている。その意味で、日本で初めての実践的なシステム思考の本だと言っても良いだろう。
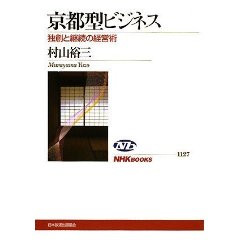 村山 裕三「京都型ビジネス―独創と継続の経営術 (NHKブックス) 」、日本放送出版協会(2008)
村山 裕三「京都型ビジネス―独創と継続の経営術 (NHKブックス) 」、日本放送出版協会(2008)
お奨め度:★★★★
やっぱり、京都だ!
京都は戦後ベンチャーのメッカである。グローバル展開している企業が多い。日本の中では唯一、東京を向いていない企業である。彼らの多くは、まず、日本で成功し、そのあとでグローバル展開という、日本企業がかかっているグローバル展開できない症候群にかかっていない。これはすごいことだ。
行政的にも新しい。よいか悪いかは別にして、日本では官僚が仕組みを考えて、それを日本全国の自治体に水平展開していく(垂直展開というべきか?)。その中で、情報センターやインキュベーションラボ、試作ネットワークなど、京都が独自に開始し、国策として取り上げられたものがある。
なぜ、こんなことができるのか?この本にその秘密が書かれている。
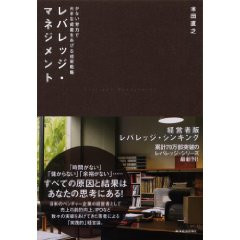 本田 直之「レバレッジ・マネジメント―少ない労力で大きな成果をあげる経営戦略」、東洋経済新報社(2009)
本田 直之「レバレッジ・マネジメント―少ない労力で大きな成果をあげる経営戦略」、東洋経済新報社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
帯に「経営者版レバレッジ・シンキング」とあるとおり、レバレッジ・シンキングをマネジメントの中で行うとこうなるというのを書いた本。レバレッジシンキングで展開された考えることによって、労力、時間、知識、人脈にレバレッジをかけて好循環を生み出すという発想が原点になった一冊。
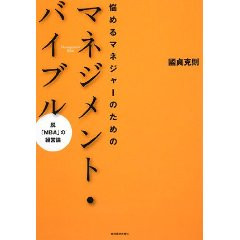 國貞克則「悩めるマネジャーのためのマネジメント・バイブル」、東洋経済新報社、(2008)
國貞克則「悩めるマネジャーのためのマネジメント・バイブル」、東洋経済新報社、(2008)
お薦め度:★★★★★
著者が自分のマネジメントに対する想いをまとめた本。書籍としてみれば決して読みやすい本ではないが、この本に書けた熱意はひしひしと伝わってくるし、何よりも述べられていることが素晴しい。書き方もよく考えられているように思う。おそらく、MBA理論の部分を除いてしまうと、結構、ありがちな経営の精神論か、成功したコンサルタントの経験論のような内容になってしまうのではないかと思うのだが、あくまでもベースはMBA理論であって、それを現場でどのように解釈し、どのように適用していくかを書いた内容になっている。
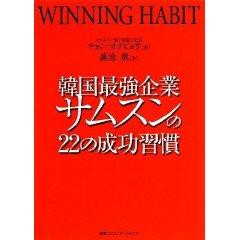 チョン・オクピョウ(蓮池薫訳)「韓国最強企業サムスンの22の成功習慣」、阪急コミュニケーションズ(2008)
チョン・オクピョウ(蓮池薫訳)「韓国最強企業サムスンの22の成功習慣」、阪急コミュニケーションズ(2008)
お薦め度:★★★★★
サムスンの伝説のマーケッタとして知られる、チョン・オクピョウがサムスン流の勝つ企業への変身の秘訣を6章22項目にまとめた本。ひとつひとつが非常に濃い内容で、サムスンの急成長が納得できる。また、蓮池薫さんが翻訳をしているが、翻訳の質が極めて高く、書かれている内容がどんどん吸収できるような感じになる。
兵法はもともと、出版物の多いテーマだが、今年1年だけで、ビジネスをテーマにした兵法の本が3冊出ている。これはちょっと驚きだ。
兵法は、中国で5世紀くらいから民衆の間で語り継がれてきた策略の教え。中国オフショアの専門家がいろいろと「中国人は、、、」といっているのを聞くと、兵法を認識しているのかといいたくなる。
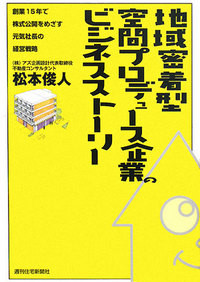 松本 俊人「地域密着型空間プロデュース企業のビジネスストーリー―創業15年で株式公開をめざす元気社長の経営戦略」、週刊住宅新聞社(2008)
松本 俊人「地域密着型空間プロデュース企業のビジネスストーリー―創業15年で株式公開をめざす元気社長の経営戦略」、週刊住宅新聞社(2008)
お薦め度:★★★★
創業し、戦略的な事業をやるというのがどういうことかを、経営者自らの経験を分析し、徹底的に教えてくれる好書。
最近のコメント