ジョン・ネスビッツは、何をみて、どう考えているか?
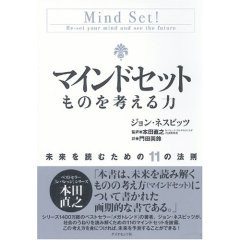 ジョン・ネスビッツ(本田 直之監修、門田 美鈴訳)「マインドセット ものを考える力」、ダイヤモンド社(2008)
ジョン・ネスビッツ(本田 直之監修、門田 美鈴訳)「マインドセット ものを考える力」、ダイヤモンド社(2008)
お薦め度:★★★★★
マインドセットは
経験、教育、先入観などから形成される思考様式、心理状態
という意味でつかわれる言葉である。人間の思考様式や、心理状態というのは一面的に捉えることはできず、多面的にとらえるために、「セット(集合)」として認識される。
まず、このマインドセットの言葉の意味を念頭において欲しい。
さて、本書は世界の未来像を描き、社会に大きなインパクトを与えた「メガトレンド」の著者、未来学者ジョン・ネスビッツが書いた未来を読み解くためのマインドセットを書いた本である。
序文の中で、ネスビッツは、私には未来が予測でき、多くの人には予測できない理由はマインドセットの違いにあると指摘し、このマインドセットを身につければ、ジョン・ネスビッツのごとく、未来を予測できると説く。
さて、そのマインドセットとは以下の11である。
マインドセット1 変わらないもののほうが多い
マインドセット2 未来は現在に組み込まれている
マインドセット3 ゲームのスコアに注目せよ
マインドセット4 正しくある必要はないことを理解せよ
マインドセット5 未来はジグソーパズルだ
マインドセット6 パレードの先を行きすぎるな
マインドセット7 変わるか否かは利益次第である
マインドセット8 物事は、常に予想より遅く起きる
マインドセット9 結果を得るには、問題解決よりもチャンスを生かすべし
マインドセット10 足し算は引き算の後で
マインドセット11 テクノロジーの生態を考える
社会的な問題だけではない。たとえば、自分の会社の将来の姿を見たいとき、自分の事業の先を考えてみたいとき、この11の視点から考えることによって、適切な未来像が見えてくるだろう。
第2部では、この11のマインドセットを用いて、実際にジョン・ネスビッツが未来図を描いてみせている。メガトレンドと似ているものもあるが、この本のマインドセットの解説を読んでから読んでみると、また、別の面白さがある。
ついでだが、この本、「レバレッジ・リーディング」の著者、本田直之氏の監訳で、コメントを寄せている。このメッセージを読むと、レバレッジ・リーディングってこういうことかって分かる(笑)。
最後にもう一つ、おまけ。本書に併せたわけでもないだろうが、未来のリーダーシップ論として、ピーター・センゲの「出現する未来」とともに注目されているハワード・ガードナーの「Five Minds for the future」が翻訳された。
 ハワード・ガードナー(中瀬 英樹)「知的な未来をつくる「五つの心」」、ランダムハウス講談社(2008)
ハワード・ガードナー(中瀬 英樹)「知的な未来をつくる「五つの心」」、ランダムハウス講談社(2008)
この本もいずれ書評しようと思うが、この本は、未来のリーダーは
・熟練した心
・統合する心
・想像する心
・尊敬する心
・倫理的な心
の5つのマインドセットが必要だと説いている。未来リーダーを目指す人は併せて読んでみてほしい。
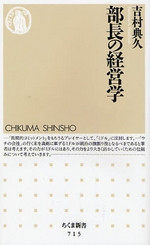
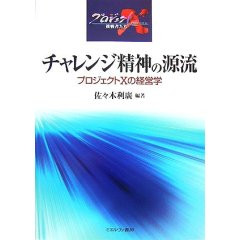
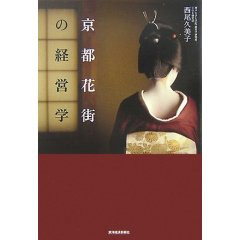
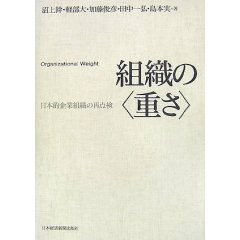
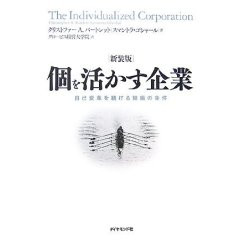
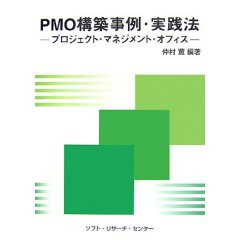
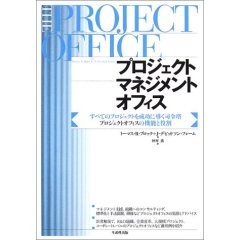
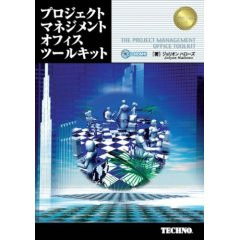
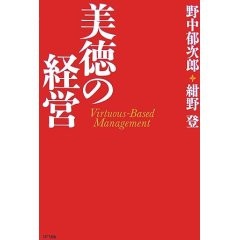
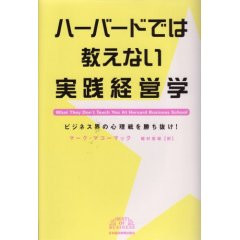


最近のコメント