リーダーシップの5レベル。あなたはどのレベル?
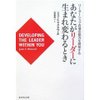
お奨め度:★★★★1/2
日本ではあまり知られていないが、リーダーシップのグル(権威)であるジョン・マクスウェルのリーダーシップ育成の名著「Developing the leader within you」の翻訳。リーダーシップ育成の方法が体系的にまとめられており、使い勝手の良い本だ。
この本のベースになっているのは、リーダーシップの能力レベル。これがなかなか興味深いので、抜粋しておく。
レベル1:地位
権利。部下が従うのは義務だから
レベル2:相互理解
人のつながり。部下が従うのは、それを望んでいるから
レベル3:成果
結果。部下が従うのは、組織のために積み上げられたリーダーの実績を評価しているから
レベル4:人材育成
再生産。部下が従うのは、リーダーが彼らのためにしたことを、部下自身が評価しているから
レベル5:人間性(人間味)
尊敬。人がついてくるのは、リーダーの人となり、そしてそのリーダーが体現しているものの両方を評価しているから
この階段を昇っていく方法を示している。その示し方としてはTips(断片的な知識)を与えているので、柔軟に使うことができる。まず、自分がどのレベルにあるかを知り、何ができるようになれば次のステップにいけるかを確認し、必要なTipsを読み、実践していく。
そんな方法で使うと非常に役立つ一冊である。また、さすがはジョン・マクスウェルの本だと思えるくらい、読み応えもある。
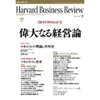







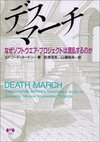
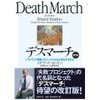
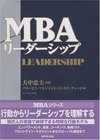



最近のコメント