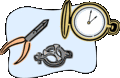=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
【目的】アカウンタビリティを果たす
【用途】メンバーに作業を分担し、責任と意欲を持って取り組ませる
【効用】メンバーが意欲で作業に責任を持つことにより、高い品質の成果物を期待できる
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
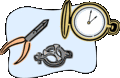
◆プロジェクトにおけるメンバーの責任
リーダーシップの役割の中で、重要なことはメンバーに責任を委ねることである。責任には、アカウンタビリティとレスポンシビリティの2種類がある。アカウンタビリティは成果責任(あるいは、成果の説明責任)であり、レスポンシビリティは実行責任を意味する言葉である。
米国と日本の感覚の差があるが、米国的なプロジェクトマネジメントの考えとしては、アカウンタビリティはプロジェクトリーダーが持つ。プロジェクトリーダーはアカウンタビリティを果たすための計画を策定し、その計画のレスポンシビリティをメンバーに委任される。そのために、RAM(責任分担表、Responsibity Assignment Marix)を作成する。
従って、メンバーがレスポンシビリティを果たし、計画通りに作業を進めていき、成果が十分でなかった場合には、その責任はプロジェクトリーダーが負うことになる。それ以上でもそれ以下でもない。
日本的な感覚としては、レスポンシビリティはメンバーにあるが、アカウンタビリティはプロジェクトマネジャーにあると考えるのは少し違うかもしれない。日本の組織の文化は誰も責任を取らない、言い換えると、メンバーに責任を押し付けた上で不問にする文化である。アカウンタビリティはプロジェクトの連帯責任になると考えるの自然だろう。
そのような感覚の違いがあることを先にお断りした上で、どうあるべきかを議論したい。
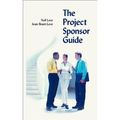 Neil A. Love、Joan Brant-Love「The Project Sponsor Guide」、Project Management Inst (2000/07)
Neil A. Love、Joan Brant-Love「The Project Sponsor Guide」、Project Management Inst (2000/07)