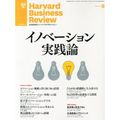【PMスタイル考】第53話:プロジェクトのコンセプトとデザイン
 ◆デザインという言葉の意味
◆デザインという言葉の意味デザインという言葉が市民権を得てきました。デザインという言葉は、典型的なカタカナ英語の一つで、従来、分野によってその意味するところが微妙に異なる言葉でした。
美術工芸品・工業製品などの世界では、形・色・模様など、いわゆる「意匠」という意味でデザインという言葉は使われています。図案という言い方をすることもあります。一般的にもこの意味がもっとも通りがよいのかもしれません。
技術の世界では、機能、方式、構成などの「設計」の意味で使われます。この場合、意匠と比べると、抽象度の高い使い方になります。この世界では、デザインという言葉より、設計という言葉の方が通りがいいようで、設計というと、機能の設計を意味することが多いように思います。
デザインという言葉は、何かを決めること、つまり、意思決定ですが、工夫をめぐらすというニュアンスが強くあるように思います。工業製品で使う意匠という言葉は、意も匠もそういうニュアンスの言葉で、含蓄があります。モノの形を決めるというのは、単に形状を決めているだけではありません。たとえば、カトラリー(洋食器のうちナイフ、フォーク、スプーンなどの金物類)を考えてみるとよく分かります。デザインは形と機能を決めます。そして、形は性能を構成しています。賛否はあるようですが、先割れスプーンなどはその典型だといえるでしょう。