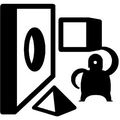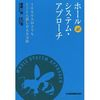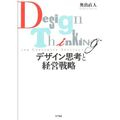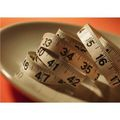【PMスタイル考】第47話:プロジェクトリーダーとしての「権威」を高めるためには
 ◆プロジェクトリーダーには権限が少ない?
◆プロジェクトリーダーには権限が少ない?
プロジェクトリーダーに関してよく問題になることに、権限の問題があります。多いのは、プロジェクトリーダーには与えられる権限が少ないのではないかという不満です。
プロジェクトは本来、権限で動かすものではありません。大規模なプロジェクトになればなるほど、難しいと言われるのはこの点においてです。では、プロジェクトは何で動かすのか。
大きく分けると2つあると思われます。一つは、「権威」です。もう一つは、「対人関係」です。
この点をまず、念頭においてこの話を少し整理してみたいと思います。プロジェクトは権限で動かすものではないといいましたが、正確にいえば、権限だけでは不十分、言い換えると、プロジェクトを動かすのに十分な権限は与えられないということです。プロジェクトリーダーを組織職と明確に関係づけている、たとえば、プロジェクトリーダーは主任級以上といった場合には、組織職に見合うプロジェクトリーダーに権限を与えることがあります。しかし、これは便宜的な話であって、組織職の権限だけではプロジェクトがうまくできそうもないので、プロジェクトリーダーを決めてプロジェクトで業務を遂行するわけですので、本末転倒です。
プロジェクトリーダーの権限ということでいえば、プロジェクト憲章をつくるプロセスで上位組織と「権限闘争」を行い、獲得するのが本来の姿です。つまり、プロジェクトリーダーの権限は、プロジェクトによって異なるということです。プロジェクトリーダーが事業部長並みの権限を持つプロジェクトがあってもおかしくありませんし、まったく権限がなくてもおかしくありません。あくまでも、プロジェクトの属性に応じて、組織として判断し、決定すべきことです。
ただ、プロジェクトリーダーにそんな大きな権限を持たせることは現実的ではありません。そこで、冒頭のような不満がでてくるわけです。