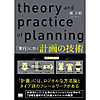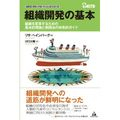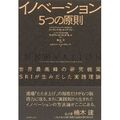PMstyle2013
2013年度は、PMstyle はじまって以来の最大の変化の年になります。変化の方向性は
プロジェクトマネジメントからマネジメントへ
です。
プロジェクトマネジメントをやめようということではなく、プロジェクトが普通の業務形態になってきた現状を踏まえて、如何にプロジェクトを成功させるかをプロジェクトマネジメントよりももっと広い視点、つまり、マネジメントという視点から考えていくという方向性を目指します。
この方向性で、
・プロジェクトの活用講座
・コンセプチュアルスキル講座
・イノベーション講座
・リーダシップ講座
・不確実な状況におけるプロジェクトマネジメント手法
・プロジェクトマネジメント技術
という6つのカテゴリーを設定しました。ここでは各カテゴリーについて概要を紹介し、各講座の紹介については別途紹介したいと思います。