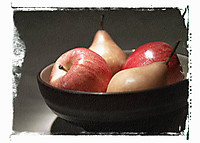【PMstyle Column:004】水野和敏さんの「思考作り」
 12月12日の日経ビジネスオンラインの連載「フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える」に台湾「LUXGEN」の責任者に就任した水野和敏さんへのインタビュー記事が取り上げられていました。
12月12日の日経ビジネスオンラインの連載「フェルディナント・ヤマグチの走りながら考える」に台湾「LUXGEN」の責任者に就任した水野和敏さんへのインタビュー記事が取り上げられていました。
緊急速報!GT-R水野和敏氏が台湾自動車メーカーに!【番外編】水野和敏氏インタビュー・前編
水野氏、台湾「LUXGEN」の開発責任者に【番外編】水野和敏氏インタビュー・後編
このインタビューがとても興味深いものだったので、水野さんの発言を引用しながらコメントしたいと思います。