人やチームの問題解決能力を向上させ、問題を解決する方法

お奨め度:★★★★1/2
問題解決法は定着してきた感があるが、通常の問題解決プロセスでは解決できないような制約条件の厳しく、前例がないような問題に遭遇することは少なくない。
世の中のどこにもないようなサービスや商品や技術を開発するといったものも、もちろん、その類の問題だが、もっと身近なものが多い。
例えば、普通にやれば1ヶ月かかる仕事を2週間でやらなくてはならないとしよう。
このようなタイプの問題では、おそらく、問題解決手法を適用しても、答えは出てこない。通常の問題解決法は、定型的問題解決法だからだ。従って、まったく未知な問題に遭遇したときには意外と無力である。
どこに違いがあるのか?大きくは問題解決の目的の違いかもしれない。前者には答えがあるので、問題解決プロセスを間違えなければ問題は解決できる。後者のような問題では、人やチームに焦点を当てる必要がある。当初の人やチームの問題解決能力では対処ができないわけであるので、それを改善しながら問題解決をしていくことを考える必要があるのだ。
このようなタイプの問題解決方法はCPSと呼ばれる。Creative Problem Solving、創造的問題解決である。
あまり日本ではCPSの本は出版されていないが、やっと良い本が出てきた。この本を読めば、とりあえず、考え方などが分かるだろう。ツールも豊富に紹介されており、後は、紹介されているツールを使って実際にやってみよう。







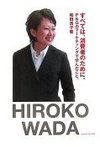





最近のコメント