キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!マインドマップ
 トニー・ブザン(神田昌典訳)「ザ・マインドマップ」、ダイヤモンド社(2005)
トニー・ブザン(神田昌典訳)「ザ・マインドマップ」、ダイヤモンド社(2005)
お奨め度:★★★★1/2
最近、注目されているマインドマップだが、提唱者のトニー・プザンの原典がついに翻訳出版される。訳が、神田昌典氏というのも心憎い。最後に神田氏による解説もある。
この本はマインドマップというツールの唯一の公式書であり、出版ライセンスだけではなく、マインドマップのディストリビューターライセンスのようなものが必要らしく、それを今回、ダイヤモンド社が取得し、書籍の出版にこぎつけたらしい。
日本では、トニー・ブザンの本としては、放射思考によるノート術というのが最初だと思う。例のドラゴン桜で話題になった方法を紹介した本である。
 トニー・ブザン(田中孝顕訳)「人生に奇跡を起こすノート術―マインド・マップ放射思考」、きこ書房(2000)
トニー・ブザン(田中孝顕訳)「人生に奇跡を起こすノート術―マインド・マップ放射思考」、きこ書房(2000)
この本はアマゾンでは極めて評判がよい。
ところがこの後、ブザンのコミュニケーションの本が出ている。
 トニー・ブザン(田中孝顕訳)「コミュニケーションに奇跡を起こす マインドマップ活用術」、きこ書房(2005)
トニー・ブザン(田中孝顕訳)「コミュニケーションに奇跡を起こす マインドマップ活用術」、きこ書房(2005)
なのだが、この本はあまり、評判がよくない。書かれていることはともかくとして、書いてあることとマインドマップとの関係が分からないという意見が多い。
しかし、今回、出版された、原典を読めば、この本で言っていることもちゃんとマインドマップの思想を組んでいることが分かる。
マインドマップはツールだと思っている人が多い。もちろん、ツールなのだが、どのような思想で設計されたツールなのかを知るには、この原典を読むのが一番である。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!






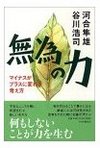
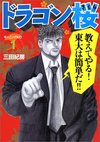



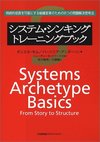

最近のコメント