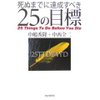 中嶋秀隆、中西全二「25の目標」、PHP研究所(2007)
中嶋秀隆、中西全二「25の目標」、PHP研究所(2007)
お奨め度:★★★★1/2
むかし、神戸大学の経営大学院で加護野忠男先生のマネジメント論の授業を受けた際に、非常に印象に残った言葉があった。それは、「マネジメントは生き様である」という言葉だ(もはや、講義のタイトルすら覚えていないので、この言葉はよほど印象に残ったのだと思う)。
中嶋さんと中西さんのこの著書を読んだときに思い出したのが加護野忠男先生のこの言葉だった。この本で書かれている人生をプロジェクトに見立てたプロジェクトマネジメントの考え方がまさしく、中嶋さんや中西さんの生き様なのだろうなと思ったのだ。
この本は前半は、人生の目標(25の目標)の定め方、後半は定めた目標の実行の方法について述べられている。
前半では、
・自分の人生のビジョン
をつくり、そこから、
・25の目標
に落とし込む。そして、そのうちの目標のどれかをうまく達成したら
・人生101のリスト(思い出リスト)
に書き込んでいくというスキームを提案している。そして、実際にこれらがツールとして提示されており、ワークをしながら読んでいけるような形になっている。
後半では、お二人の活動されている会社(プラネット)が提唱しているPM10のステップを使って、設定した目標を如何に達成するかが解説されている。
前半と後半をあわせて、人生をプロジェクトマネジメントするということになる。
実は、この本、著者の1人の中嶋さんから昨年の末に頂戴したのだが、このブログに書評を書くのに1ヶ月近くの時間が過ぎてしまった。とりあえず、さっと読むのはすぐにできたが、せっかくだと思い、25の目標を作り出した。作り出すと、いろいろなことが頭に浮かんできて、何度も読み直しながら、やっと先日作り終えて、こうして書評を書いている。
このような経験を通じて分かったことは、実際に目標を作ってみると、前半の目標設定の中で書かれていることが実によく分かるし、中嶋さん独特(?)のものの見方もだんだん、腑に落ちてきた。また、25が一種のマジックナンバーではないかとも思えるようになった。論より行動である。
ということで、この本を読まれる方は、実際に演習をやってみないと価値が半減する!とアドバイスしておきたい。ぜひ、25の目標を立て、その達成チャレンジを実践してみてほしい。
もうひとつ、この本は記述が極めて良質である。帯に「PMのプロ講師直伝」と書かれているのは、内容もそうだが、教える方法に対する自信の表れなのだろう。
もうひとつ読者の方へのアドバイス。前半で提案されている目標設定と達成のスキームはプログラムである。この本では、「ダイナミックに全体のバランスをとる」と書かれている。実は、このダイナミックにバランスをとる具体的な方法が後半でもあまり明確になっていない(ヒントはある)。
この本の後半に書かれている(シングル)プロジェクトマネジメントだけではなく、プログラムマネジメントの手法を習得すると、一層、25の目標がよりうまく達成できるのではあるまいか。この本を読んでプロジェクトマネジメントが一通り分かったら、次はその辺りを勉強してみてほしい。
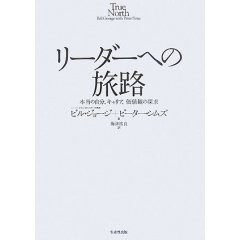 ビル・ジョージ、ピーター・シムズ(梅津祐良訳)「リーダーへの旅路―本当の自分、キャリア、価値観の探求」、社会経済生産性本部(2007)
ビル・ジョージ、ピーター・シムズ(梅津祐良訳)「リーダーへの旅路―本当の自分、キャリア、価値観の探求」、社会経済生産性本部(2007)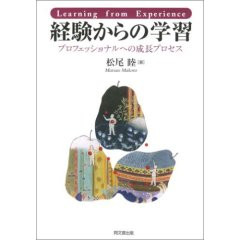
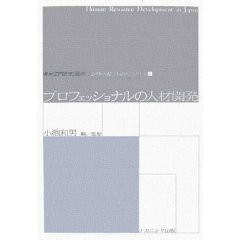
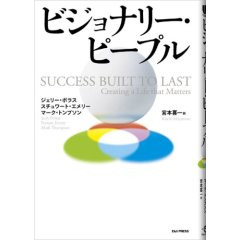
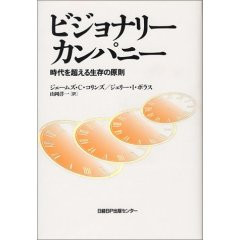
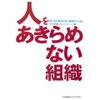
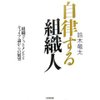
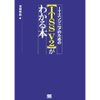


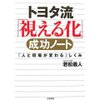
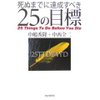

最近のコメント