極めろ上司道!
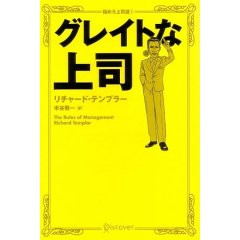 リチャード・テンプラー(米谷敬一訳)「極めろ上司道1 グレイトな上司」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2007)
リチャード・テンプラー(米谷敬一訳)「極めろ上司道1 グレイトな上司」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2007)
お奨め度:★★★★
マネジメントの基本を100のルールとして体系的に示している。非常に軽い口調で、抵抗なく受け入れられると思う。新任のマネジャーの座右の書にしてほしい一冊。
Part1はグレイトなチームをつくれ(チーム管理編)。
利益を語るな、貢献を語れ
自分を語るな チームを語らせろ
非現実的な目標から部下を守れ
成功はすべてチームのおかげと主張せよ
など、かなり本質的なことが、並んでいる。いわゆるチームマネジメントの本に書いてある常識とは少し異なる点が興味深い。
Part2はグレイトな上司であり続けろ(自己管理編)
懸命に働け
部下が憧れる手本となれ
仕事を楽しめ
家族を大事に 早く家に帰れ
など、こちらもやはり、一風変わったルールが並んでいる。
ちなみに、このシリーズには3部あるらしいが、すでに第2弾は出ている。
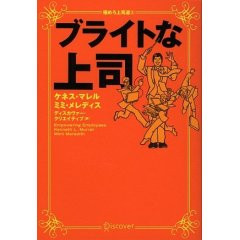
ケン・マレル、ミミ・メレディス(ディスカバリー・クリエイティブ訳)「極めろ上司道2 ブライトな上司」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2007)
著者は異なるが、同じようなテーストで、こちらはスポンサーとしての上司がテーマになっている。
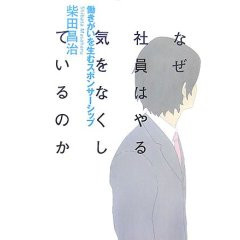
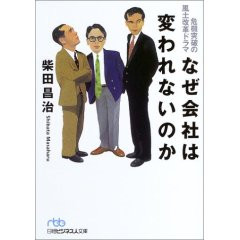
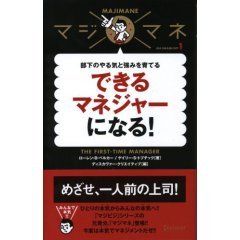
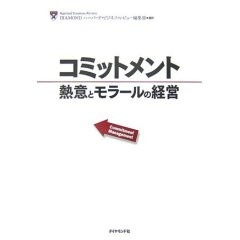
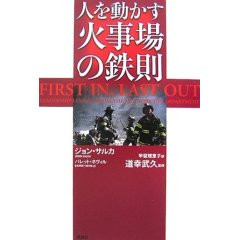
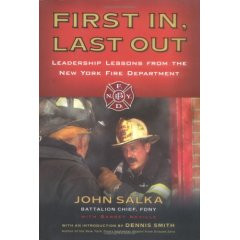
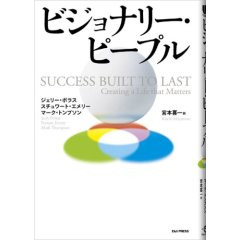
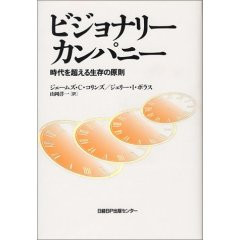
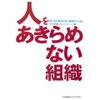




最近のコメント