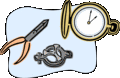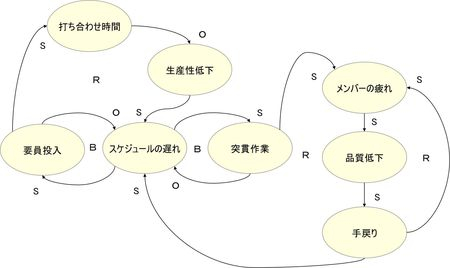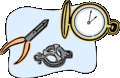【UserStyle】ユーザ主導型プロジェクトの編成とマネジメント(1)~イントロダクション
◆ユーザ主体開発
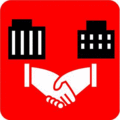 日経BP社の谷島宣之さんがITの開発で提唱されている「ユーザ主体開発」を提唱されている。7月には谷島さんが編集された書籍も発売された。
日経BP社の谷島宣之さんがITの開発で提唱されている「ユーザ主体開発」を提唱されている。7月には谷島さんが編集された書籍も発売された。
日経コンピュータ「開発・改良の切り札 システム内製を極める」、日経BP社(2011)
この概念は、情報システムの開発の中で、ユーザが主体性を持つべき範囲を明確にし、その開発業務については徹底して内製化を図ることによって、業務のベネフィットを高めようするものである。これからの日本企業が、グローバルな競争を勝ち抜いていくためには極めて重要な概念である。
そこで、この連載では、ユーザ主体開発をスムーズに推進していく、ユーザ主導型プロジェクトマネジメントについて考えてみたい。