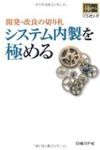PMstyleでは、これから、ユーザ主導型プロジェクトマネジメント(UserStyle)というコンセプト提案をしていきます。
その最初の取り組みとして、コンセプトの解説を行う連載記事「ユーザ主導型プロジェクトの編成とマネジメント」を開始しました。
このコンセプト提案を行う契機になったのが、日経コンピュータの前編集長の谷島宣之さんが過去の取材記事をベースにまとめられた本です。
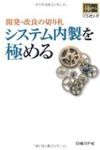 日経コンピュータ「開発・改良の切り札 システム内製を極める」、日経BP社(2011)
日経コンピュータ「開発・改良の切り札 システム内製を極める」、日経BP社(2011)
書籍の詳しい内容はビジネス書の杜の紹介記事をお読みください。
情報システムにおける「ユーザ主体」とはどういうことか
この本で提唱されている「ユーザ主体開発」は今後、極めて重要になってくると思われれるビジネス活動です。
これまでも、企業情報システムを内製化すべきかどうかは、ずっとあった議論です。この本は、本書用の新規取材を含めて、これまでの日経コンピュータ の取材記事に基づき書かれています。その中には、5年以上前の事例も含まれています。そのくらい前からあった議論です。そのほとんどは、技術的な観点から の議論でした。
しかし、ユーザ主体というのは内製化の議論を超え、マネジメントの議論を含みます。つまり、開発するかどうかが必ずしも問題ではなく、主体性を持って情報化を行うのか、提供されるものを使うのかの議論です。
この議論は、戦略実行はもちろん、戦略策定にも大きな影響を与えます。その意味で、今後、重要になってきます。そのような視点から、ユーザ主体開発を行うためには、どういうマネジメントが必要というのが上に紹介した連載記事のテーマです。
その連載開始の記念としても、本書のプレゼントを行います。プレゼントを希望される方は、以下の応募ページから応募ください。
書籍プレゼント「内製を極める」応募ページ
https://mat.lekumo.biz/pmstyle/present.html
なお、本プレゼントとは別のプレゼントとして、ビジネス書の杜でも同じ本のプレゼントをしています。どうしても、手に入れたいという方は、ビジネス書の杜の方にも応募してください!
ユーザ主体の情報化に関する本を2名様に!(第74回ビジネス書の杜書籍プレゼント)