あるあるマーフィー探検隊!
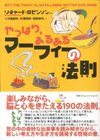 リチャード・ロビンソン(小林由香利、杉浦茂樹、服部真琴訳)「やっぱり、あるある マーフィーの法則」、阪急コミュニケーションズ(2005)
リチャード・ロビンソン(小林由香利、杉浦茂樹、服部真琴訳)「やっぱり、あるある マーフィーの法則」、阪急コミュニケーションズ(2005)
お奨め度:★★★★
マーフィーの法則とは、先達の経験から生じた数々のユーモラスでしかもペーソスに富む経験則をまとめたものである。「マーフィー」と言う名は、基地内のライト航空研究所に勤務していたエンジニアのエドワード・アロイシャス・マーフィー大尉が残したエピソードに端を発するといわれている。マーフィー大尉の逸話とは
エドワード空軍基地に来ていたマーフィーは、トラブルを起こした装置を調べて誰かが間違ったセッティングをしていた事を発見し、
If there is any way to do it wrong, he will.「奴は可能な限りヘマをする」
と言い放った。ここからマーフィーの法則は始まり、冒頭に述べたような法則をマーフィーの法則と呼ぶようになったという。
その後、いろいろな人の手で、マーフィーの法則が作られている。この本もその一冊。なかなか、よく出来たマーフィーの法則が多い。この本の中で、印象に残ったのは、帯にあるものだが、
・結論とは考えるのに飽きたときにたどり着く場所だ
・好きなようにしていいとき、人は誰でも同じことをする
といった法則である。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!







最近のコメント