創造的模倣
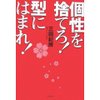 三田紀房「個性を捨てろ!型にはまれ! 」、大和書房(2006)
三田紀房「個性を捨てろ!型にはまれ! 」、大和書房(2006)
お奨め度:★★★★
ご存知、偏差値30台の高校生が現役で東大合格を目指す異色コミック「ドラゴン桜」の三田紀房氏の啓蒙書。三田紀房氏は、ドラゴン桜以外にも、ボクシングの世界チャンピオンがビジネス界でのチャンピオンを目指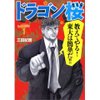
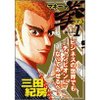 す「マネーの拳」というコミックスも書いている。
す「マネーの拳」というコミックスも書いている。
著者によると、コミックスではなく、もっと直接的に言いたいので本にしたとのこと。
ドラゴン桜にもマネーの拳にも共通する違和感がある。それは、「型」に対するこだわりと、組み合わせに対するこだわりだ。
世の中には成功するための型があり、成功するためには型にはまる必要があることを徹底的に主張している。これは著者の独自の主張というよりは、むしろ、多くの成功本で言われていることだ。
そして、より大きな成功をするには、その組み合わせが重要であるという2点。ここは、著者のオリジナリティだと思う。
誰もできないことをやるのは快感である。しかし、誰もできないことをやるよりは、成功していることがやっていることを「確実」にやるほうが難しい。競争するというのは結局そういうことであり、型にはまれという話は競争を恐れるな、同じ土俵で競争して勝てという王道を主張しているようにも思える。
もう、10年以上前になるが、この話を実証するような本が出版されている。
 スティーヴン・P. シュナース(恩蔵直人、嶋村和恵、坂野友昭訳)「創造的模倣戦略―先発ブランドを超えた後発者たち」、有斐閣(1996)
スティーヴン・P. シュナース(恩蔵直人、嶋村和恵、坂野友昭訳)「創造的模倣戦略―先発ブランドを超えた後発者たち」、有斐閣(1996)
お奨め度:★★★★1/2
この本は、後発企業が先発企業を逆転している例を集め、その要因を分析し、それらの要因を持つ戦略を創造的模倣戦略と呼んでいる。
・35ミリカメラ:キャノン:ニコン
・ボールペン:パーカー、ビック
・クレジットカード:VISA
・MRI:ジョンソン&ジョンソン、GE
・パソコンOS:マイクロソフト
・表計算ソフト:ロータス(さらに後発でマイクロソフト)
・ビデオ:JVC
・ビデオゲーム:任天堂
などの企業の事例を上げている。おそらく、二番手企業というイメージの企業はないだろう。むしろ、創造性の高いというイメージを持つ企業が多い。
イノベーションが注目されているが、イノベーションの議論というのは注意する必要がある。イノベータと呼ばれるのは主に、ドミナントデザインができた後で出てきた企業である。上の例を見てもそれは良く分かるだろう。
三田紀房の言い方を借りると、ドミナントデザインができた後で競争することが、成功の型にはまるということだろう。
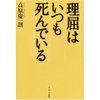


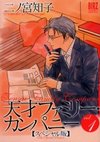


最近のコメント