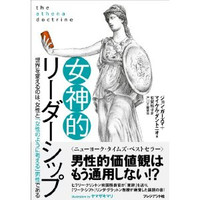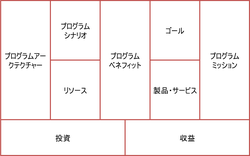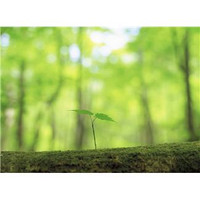【PMスタイル考】第78話:計画について考える
 ◆不確実な環境下における計画の役割
◆不確実な環境下における計画の役割
アジャイルプロジェクトマネジメントやアジャイル開発という言葉がどこの企業に行っても聞こえてくるようになってきました。は顧客価値創造によるイノベーションが実現できるというのが理由のようです。
なぜ、アジャイルが顧客の価値創造につながるのかと聞いてみると、割と多くの人がいう理由が2つあります。一つは、顧客と一緒にものを創り上げていくこと。もう一つはその点に深く関係するのですが、全体の計画ができないという理由です。
今回は不確実な環境下で計画をどのように行うのかという問題を考えてみたいと思います。もちろん、状況を見ながら次の計画を繰り返していくアジャイルはその一つの方法であることは間違いありません。そこにも関係してくる話です。