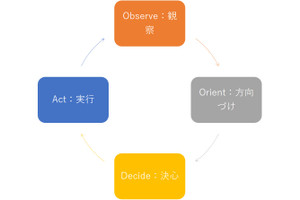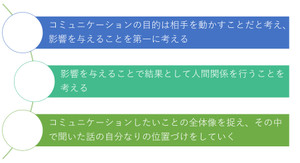【PMスタイル考】第121話:コンセプチュアル・プロジェクト・デザイン
バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末年始に読んだ本で改めて重要性を感じたことがあったので、今回のPMスタイル考はその話題を考えてみたい。
読んだ本は、「ドッグファイト」という小説で、アマゾンをモデル化したグローバルな通販企業 とクロネコらしき日本の物流企業「コンゴウ」の戦いを描いている。戦場は、生鮮食料品の同日配送を扱うシステムを構築をするプロジェクト。このプロジェクトを巡り、さまざまな駆け引きが交差し、話は進んでいくのだが、ストーリーを知りたい人は本を読んで欲しい。
この中で、「スイフト」社のプロジェクトの進め方として、「コンセプチュアルデザイン」という概念が出てくる。これは、プロジェクトの目指す成果物とオペレーションを明確にし、それをドキュメント化したもので、プロジェクトのコアメンバーが共有すべきプロジェクトのバイブルという位置づけのものである。