技術者のためのマネジメント入門
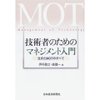
お奨め度:★★★★1/2
仕事柄、エンジニア出身のマネジャーにマネジメントの勉強をすることをお奨めすることが多い。確かにその目的に適う書籍は、日本にも結構あるのだが、視座がマネジメントにある本がほとんどである。つまり、経営の中でどのように技術を役立てていくかという視点がある。
しかし、この本は珍しく、視座が技術にある。技術を中心に経営をしていくにはどうしたらよいかを説明している。技術者に薦めたい本である。
内容もとてもよい。そんなに高度な内容ではないが、必要最小限の問題として、戦略のあり方、マーケティング活動のあり方、組織のあり方、プロジェクトマネジメントなど一通りの経営プロセスの解説がある。同時に、新事業創造、マーケティングコミュニケーション、ビジネスモデルといった事業マネジメントについても触れられている。
書き方も事例を中心にかかれており、実践的である。
特に、素晴らしいと思うのは、日本のMOTの本はなぜかあまり正面からプロジェクトマネジメントを取り上げていない。この本は経営プロセスの一つとして1章を割いて解説されている。拍手したい!
最後に、どうでもいいが、著者もなんとも豪華。編者の伊丹敬之先生、森健一先生は、もちろんだが、常盤文克先生、徳重桃子先生、佐々木圭吾先生、坂本正典先生、宮永博史先生、齊藤友明先生、西野和美先生。





最近のコメント