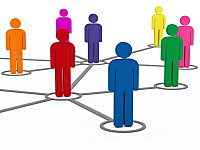【PMスタイル考】第129話:まねるとは本質を理解し、実現することである
バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆まねる
イノベーションが注目されるようになって、まねることが再び、注目されるようになっている。イノベーションは既存のアイデアの組み合わせであると言われており、まねることと非常に強い関連性があるからだ。
いい意味でも悪い意味でも、日本人はまねることが得意だといわれてきた。良い悪いは別にして、実際にまねから始めて、発展させ、新しいものを生み出してきたのは確かだろう。高度成長期はまさにそのような時期だったといえる。このあたりの話は、井上達彦先生の
「模倣の経営学 実践プログラム版 NEW COMBINATIONS 模倣を創造に変えるイノベーションの王道」、日経BP社(2017)
を読んでみるとよい。トヨタやセブン-イレブンが採った、手本とする他社の本質を見抜き、自社で生かせる儲かる仕組みを抽出する創造的な摸倣の方法を体系的にまとめた一冊だ。また、井上先生が翻訳された
オーデッド・シェンカー(井上達彦、遠藤真美訳)「コピーキャット―模倣者こそがイノベーションを起こす」、東洋経済新報社(2013)
もお勧めである。
しかし、一方で、まねはしてもイノベーションが生まれなくなっているという現実もある。どうしてなのだろうか。
そこにはまねるとはどういう行為なのかという問題があるように思える。今回のPMルスタイル考は、この問題について取り上げてみたい。