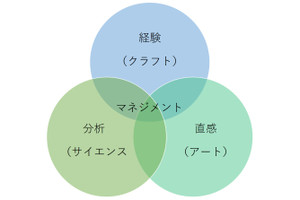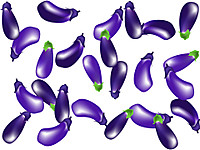【PMスタイル考】第139話:アートとテクノロジーの組み合わせとコンセプチュアル思考
バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆アート、クラフト、サイエンスの役割分担
前回のPMスタイル考では、ヘンリー・ミンツバーグ教授の
経営とは、「直感(アート)」、「経験(クラフト)」、「分析(サイエンス)」を適度にブレンドしたものである
という指摘を取り上げ、バランスを取る方法として、コンセプチュアル思考が適していることを述べた。
【PMスタイル考】第138話:直感・経験・分析のバランスの取れた意思決定を行う
https://mat.lekumo.biz/pmstyle/2018/10/poste645.html
今回は、この議論をもう少し深めてみたい。
まず最初に、前回の記事に対していただいた質問、どういう風にアート、クラフト、サイエンスの3つの要素を使うのかという問題を整理しておきたい。
これがミンツバーグ教授のいうブレンドのポイントだと考えられるが、もっともオーソドックスなのは
(1)アートにより、ビジョンが生み出される
(2)クラフトにより、ビジョンが実現される
(3)サイエンスにより効率化されていく
という役割分担だろう。